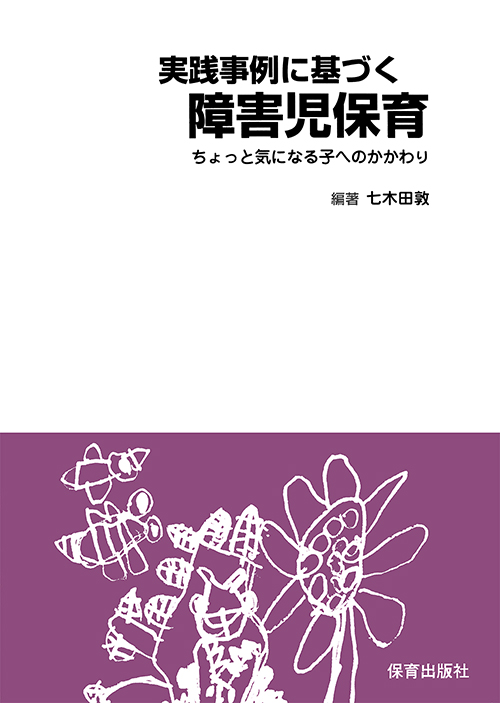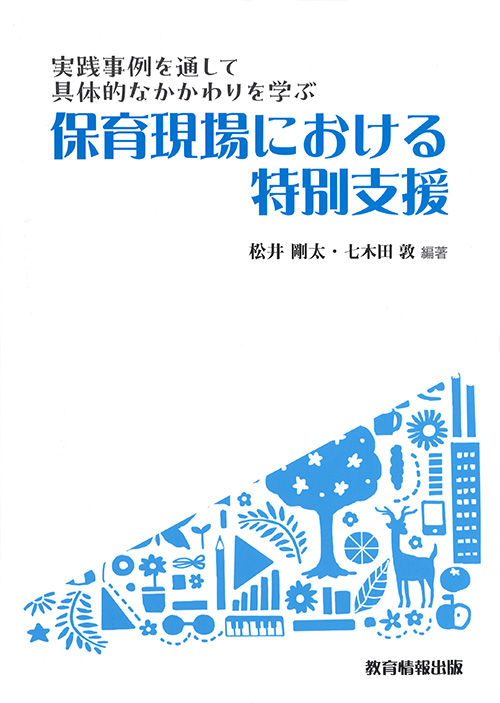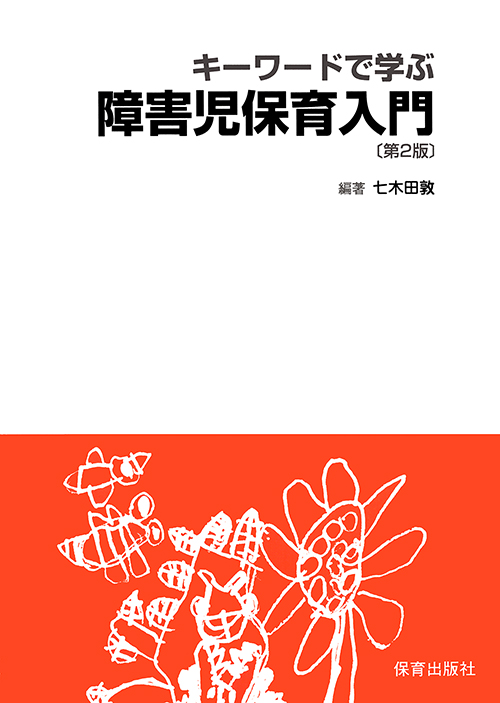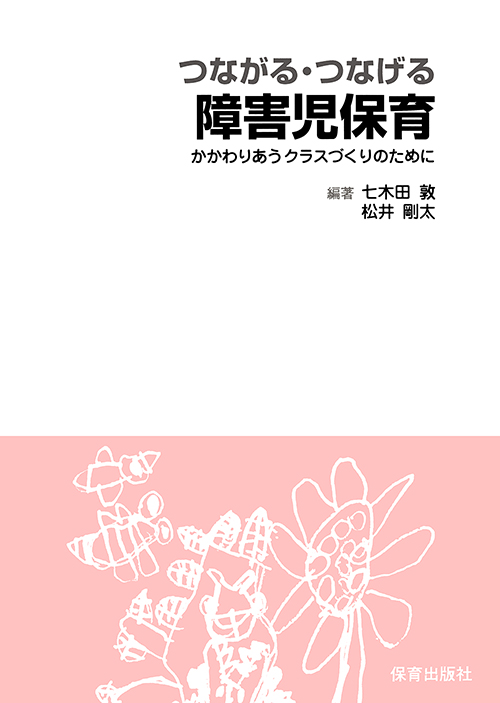
つながる・つなげる障害児保育 -かかわりあうクラスづくりのために-
| 編著 | 七木田敦、松井剛太 |
|---|
| ISBN | 978-4-905493-18-1 |
|---|---|
| 体裁 | B5判 198頁 |
| 刊行 | 2017年4月 |
| 定価 | 2,497円(本体2,270円+税) |
特長
「子ども一人ひとりに配慮した保育」「情報を共有し,連携する保育」「ともに育つ保育」をコンセプトに,具体的な事例をふまえわかりやすく解説しています。
各章のはじめにポイントやキーワードをふまえた予習ができ,章末では学習した内容を振り返ることができます。さらに,巻末では課題やグループ学習などを設け,随所に自分で考え学べるような構成となっています。
目次
1章 保育と特別支援教育
- 1-1 障害のある子どもの保育とは
- 1-2 保育と特別支援教育
- 1-3 保育のなかでちょっと気になる子ども
- 1-4 発達凸凹と発達障害とは
- 1-5 かかわりの基本
- 1-6 ていねいなかかわり
2章 学習に課題のある子どもの保育
- 2-1 学習症とは
- 2-2 独特な知覚特性
- 2-3 幼児期の学習症
- 2-4 保育のなかでの学習症と配慮の工夫
- 事例を考える①「学習症のS君への配慮と工夫とは?」
- 2-5 保護者へ伝えたいこと
3章 不注意や多動が見られる子どもの保育
- 3-1 注意欠如・多動症とは
- 3-2 診断の付加価値から分かること
- 3-3 二次障害予防のため
- 3-4 保育のなかでの注意欠如・多動症と配慮の工夫
- 事例を考える②「どうしてR君は友だちに手が出るの?」
- 3-5 保護者へ伝えたいこと
4章 対人関係の課題や強いこだわりのある子どもの保育
- 4-1 自閉スペクトラム症
- 4-2 診断の難しさ-他の障害との関連-
- 4-3 こころの理論
- 4-4 保育のなかでの自閉スペクトラム症と配慮の工夫
- 事例を考える③「これじゃなきゃダメなんだ」
- 4-5 保護者へ伝えたいこと
5章 子どもとつながる,子どもたちをつなげる
- 5-1 遊び
- 事例を考える④「A君の『色探し遊び』」
- 5-2 生活習慣の形成
- 事例を考える⑤「トイレに行きたい,行きたくない?」
- 5-3 クラス活動
- 事例を考える⑥「つながる力を支援する」
- 5-4 保育者との関係-安心できる他者の存在-
- 事例を考える⑦「Sちゃんの心に添うかかわりを考える」
- 5-5 主役になる自分-自己肯定感-
- 事例を考える⑧「発表会に参加することで自信をつける」
- 5-6 行事
- 事例を考える⑨「運動会の練習でつながる・つなげる」
- 5-7 園内の連携
- 事例を考える⑩「ほかの子どもとのつながりを大切にする援助」
- 5-8 地域の専門機関との連携
- 事例を考える⑪「子どもからのSOSを見逃さないために」
- 5-9 記録と評価
- 事例を考える⑫「発達の『見えやすい側面』と『見えにくい側面』」
- 5-10 障害理解
- 事例を考える⑬「子ども同士が育ち合う場所をつくる」
6章 保護者とつながる
- 6-1 保護者の気づきと障害受容
- 事例を考える⑭「障害を認められない保護者に理解してもらうためには」
- 6-2 保護者と信頼関係を築く
- 事例を考える⑮「保護者の希望に添えなかった情報提供」
- 6-3 ソーシャルサポートネットワークの理解と活用
- 事例を考える⑯「A君と母親へのソーシャルサポートネットワークを活用した支援方法とは?」
- 6-4 ちょっと気になる保護者の特徴と対応
- 事例を考える⑰「過保護な保護者に理解してもらうためには」
- 6-5 保護者とつながるちょいテク
- 事例を考える⑱「家庭と保育所の新たな情報交換とは?」
7章 小学校へつなげる
- 7-1 小学校へとつなげることの難しさ
- 7-2 アプローチカリキュラム,スタートカリキュラムの取り組み
- 7-3 特別支援教育コーディネーターとつながる
- 7-4 就学指導を受けるときのポイント
- 7-5 就学支援シートの作成と活用